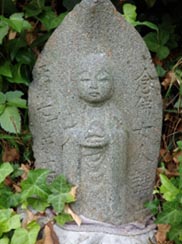瀬戸市上品野町1020
尾張城東西国三十三観音 第二十九番札所。天台宗寂場山菩提寺。菩提寺は160年前、養海上人によって開基された。本堂は千手観音菩薩を奉り、不動明王・毘妙門天・弘法大師・役行者(えんのぎょうじゃ)が安置されている。本堂東には、出雲大社より招神の神「えびす」様を迎えお奉りしてある。菩提寺は国内でも有数な霊山で、加持祈禱の道場でした。昭和4(1939)年に本堂が焼失し、今の本堂は昭和36(1961)年に再建された、菩提とは「正しく最上の覚り」という意味である。参道と本堂の間には、阿形・吽形の一対の仁王像がある山門があり、昭和46(1671)年に再建された。
張州雑志には、「当寺ハ行基大士ノ開基、華厳ノ道場也。行基大士中品野鳥原ノ岩窟(岩屋堂)ニ間棲ノ時…(中略)…千手千眼ノ尊像(千手観音菩薩像)ヲ彫刻アリテ、是ヲ安置セラル」との行基伝説が載っている。
寺伝では、天平年中(729~749)に創建された華厳宗の寺とされている。その一方で、750年頃に養海上人が創建したお寺とも伝えられ、参道石段の右横にある石碑「東照上人塔」には養老年中(717~724)当寺の建立と彫られている。
境内には88ケ所の平場がみられ、中世の12世紀末~16世紀の沢山の遺物が採集され数々の宗教施設があったことが伺われる。
本堂の裏には、ツクバネガシの巨木があり、瀬戸の名木に選定されている。
参考文献 瀬戸市史編纂委員会『瀬戸市史民俗調査報告書 四 品野地区』 瀬戸市交流活力部文化課『瀬戸の魅力発見 まちめぐりパンフレットPart13 品野地区』 瀬戸・尾張旭郷土史研究同好会『郷土史研25周年誌』 せと・まるっと環境クラブ『岩屋堂ガイドブックⅡ改訂版』