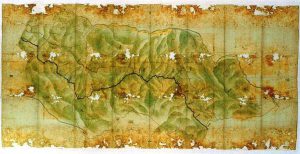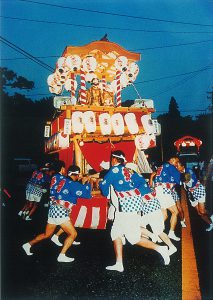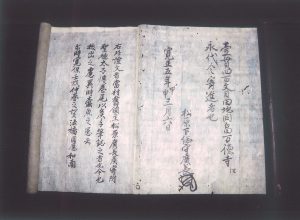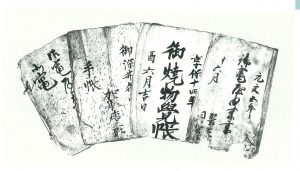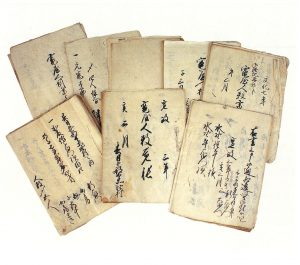瀬戸市指定建造物 1棟
平成31年3月19日指定 所在地 瀬戸市深川町
所有者 深川神社
文化財 本殿:一間社流造、銅版瓦
幣殿:切妻造、銅版瓦
拝殿:入母屋造、銅版瓦
築地塀:砂モルタル壁、藤紋役物瓦
陶彦社は、文政7年(1824)に創建された、陶祖加藤四郎左衛門景正(春慶)を祀る社である。鎮座より100年経ち、社殿すべてを建て替え、大正15年(1926)には本殿・渡殿・拝殿・礼拝所・土塀・玉垣を現在の位置に遷座した。
建築の特徴として、当時の斬新で洗練された意匠の建築美が随所にみられる。建築材には木曽檜の最良材が使われ、本殿の正面に見える虹梁などには彫刻の彫りに木目をあわせるなど、使用された材は厳選され、意匠・彫刻の技術も高く評価される。設計者の伊藤平二には名古屋の堂宮大工である9代目伊藤平左衛門(守道)の次男として生まれ、正倉院の建物の保存修理などを手掛けた。意匠には明治末から大正にかけて活躍した京都府技師の亀岡末吉の建築意匠の影響がみられ、伝統的な神社建築でありながら蟇股や木鼻などの細部意匠に西洋の意匠を取り込む近代和風建築特有の建造物で、華やかな印象を持っている。これは瀬戸市域はもとより、周辺地域にも類例が稀である貴重な和風建築である。