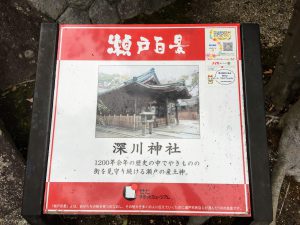瀬戸市薬師町2番地
招き猫ミュージアムは、「日本招猫倶楽部」の世話役をつとめる板東寛司・荒川千尋夫妻の個人コレクション数千点を展示する、日本最大の招き猫博物館。前身の「日本招猫倶楽部 招き猫ミュージアム」は、群馬県吾妻郡嬬恋村にあった。
平成17年(2005)3月、より多くの方々に広く招き猫の魅力を知ってもらいたいという夫妻の願いから、平成8年(1996)から官民をあげて「来る福招き猫まつりin瀬戸」の開催に取り組んできた瀬戸市に移転する運びとなった。
ミュージアムの企画運営の主体は、「来る福招き猫まつりin瀬戸」の立ち上げメンバーでもある陶磁器メーカー、株式会社中外陶園がつとめている。
ミュージアムの建物は、大正時代の瀬戸の洋館建築を彷彿させる。印象的な外観は、瀬戸中心市街地の新たなランドマークにもなっている。地元の造形作家・小澤康麿氏によるタイルや立体作品など、建物の細部にほどこされた猫の装飾を探す楽しみもある。
招き猫コレクションは、1)歴史 2)寺社もの 3)郷土玩具 4)主要産地別 5)珍品 6)雑貨などに分類され、日本文化の一面を伝える見ごたえのある展示となっている。
開館時間:午前10時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)
休館日:火曜日
入場料:大人300円、高・大学生200円、中学生以下無料